
当「社会構造変動論分野」は社会学を専門的な基礎とした研究室です。
「人間社会情報科学専攻」のなかにあり、政治情報学分野とともに「社会政治情報学講座」を構成しています。
組織としては以下のようになります。
- 情報科学研究科 > 人間社会情報科学専攻 >
社会政治情報学講座 > 社会構造変動論分野

当「社会構造変動論分野」は社会学を専門的な基礎とした研究室です。
「人間社会情報科学専攻」のなかにあり、政治情報学分野とともに「社会政治情報学講座」を構成しています。
組織としては以下のようになります。
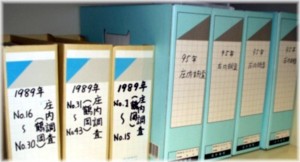
ここにいう「社会」とは・・・
本研究室で「社会の構造」というのは、上のような語義の世界における人々の行為の型を言います。
具体的に・・・
「情報」の観点からしても、これらは重要な要因であるにちがいありません。

理論研究は当研究室の重要な基礎の一つです。
当研究室の資源として、
1.学説研究の系譜があります。
とくに、古典の意義を重視しています。ゼミなどでは、A=スミス、K=マルクス、M=ウェーバー、E=デュルケム、G=ミード、T=パーソンズ、E=ゴフマン、J=ハーバマスといった古典的な社会学者の遺産を基礎からじっくり読んでいます。
もっとも、それは現代社会学の今日的な展開と結びつけ、また、リアルな課題に挑戦するため。
古典を重視するのは、「根本問題」に触れているからです(だから古典として今日に残っているのであって、ただの古い本ではありません)。とくに、その「問いの立て方」、「論理のすすめ方」、根本的な「発想法」、つまり、広い意味での方法論において継承し、今日的な考えのヒントにしているのです。
ですから、古いものにただ沈潜していているわけではありません。古典がそのまま現代に通用するわけではないからです。
今日の社会で観察される様々な事象を読み解く上で、古典から学び得るもの、現代の課題を解決する上でのヒントを導き出していきます。
さらに、古典的社会学から始まって、当研究室では、シンボリック相互作用論、エスノメソドロジー、コミュニケーション論、エスノグラフィー……の現代的展開、などを視野に入れています。
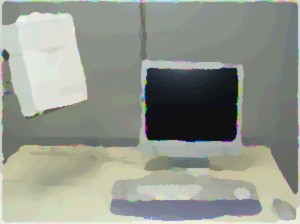
フィールドワークも本研究室の主たる関心事です。デスクワークとフィールドワークは車の両輪といってもかまいません。
当研究室には具体研究の流れとして、
2.農村社会学の系譜があります。
3.相互行為論の具体的展開も図っています。
4.市民社会論の展開、とくにNPO・NGOといった市民活動の分析もおこなってゆきます。
いずれにせよ、社会的リアリティの論理をつかむために、広義の質的研究法を中心に、フィールドワークや具体研究を展開しているのです。
具体的には、
……などの方法・方法態度によって研究を進めています。
といっても、質的研究と量的研究を対立的に考えているわけではありません。必要に応じて組み合わせることもあります。両者の関係は相補的なのであって優劣とか相互排他ではないと考えます。
2019年04月09日最終更新